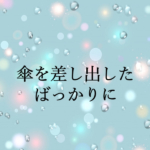金曜の約束
卒業(後日談)
一年の夏から始まったこの関係は三年の後期まで続いていた。もうLINEのやり取りすらなく、俺たちは十九時、噴水前で待ち合わせて一緒に抱き合いながら眠り、起きたら触れるだけのキスをする。
そのおかげで進学するのに十分なお金は貯まった。タンス預金だから役所に知られることもない。
俺のことが好きだと言ったのはあの一日だけだった。
戸惑う俺に配慮してるのか、何なのかはわからないが、ずっと続いているこの関係を思うときっとカカシは俺を好きなままでいるんだろうなと思う。
いつしか一緒に抱き合って眠ることが当たり前になって、安心感すら感じて、胸が満たされるようになっていった。
俺はカカシのことが好きなんだろうか。
それともやっぱりただの都合のいい金蔓なんだろうか。
そんな疑問には蓋をして、ただただ毎週抱きしめ合った。
卒業式を間近に控えたその日、俺が高校生としてカカシに会うのが最後になる日。いつものように十九時に噴水前で待ち合わせると、俺たちはホテルに入って行く。
「こうしてあんたと会うのも、今日で最後だな。」
カカシは背を向けたままジャケットを脱いでいる。
「今日も、いつも通りでいいよ。三時間、ハグとキス。」
「カカシは……いいのか。これで終わりで。」
「……うん、もう会えないのは寂しいけど、いいよ。」
振り返ったその顔は、いつもの笑顔で。
胸が、締め付けられるような気持ちになった。
「……最後、だから……。今日は何しても良い、って言ったら?」
カカシが目を見開いた。
「それ、どういう意味……?」
「ずっと俺のことを考えてくれてたんだろ。我慢してくれてたんだろ。だから、最後くらい、好きにさせてやるって言ってんだよ。」
「でもサスケ、嫌……なんじゃ、ないの? その……するの。」
「……あんたなら、別にいい。」
カカシがヒタ、とサスケに近づき、立ったまま抱きしめる。
「……本当に、いいの。なんで、俺ならいいの。ねえ、勘違いする前に教えてよ。」
「二年以上、ずっと俺のためにしてきてくれただろ。……別に、好きになったとかじゃねえからな。恩返し、みたいなもんだ。あんたとなら、……セックスも、嫌じゃない。今日は、金もいらない。俺の自由意志だ。」
抱きしめる腕が強くなる。
「好きになって、なんておこがましいことは言わない。でも、大学生になってからも男と会うのは俺だけにして欲しい。それが俺のわがままだ。それだけでいい、それだけで、十分だよ。」
「……何だよそれ……何もせずいつも通りでいいのか?」
「恩返しなんて、いらないよ……いつも通りに、一緒に寝て、キスして、お金渡して、それで俺たちの関係は終わり。……じゃないと、サスケのことが忘れられなくなるだろ。」
サスケもカカシの背中に手を回す。
「俺のこと、忘れたいのか? 俺は、忘れらんねぇよ。ずっと俺のために居続けてくれたあんたのこと。進学できるのも、全部カカシのお陰だ。……多分ずっと、忘れらんねぇ。忘れたくもない。」
「それ以上、言わないで。お前にとって俺は都合のいい金蔓だ。そのままでいい。特別な何かなんて必要ないから。」
「……俺にとっては、あんたは特別だ。」
抱きしめあったまま、沈黙が流れる。
カカシはサスケの背から肩に手を移し、距離を開けてサスケの顔を見た。
「そんな事、言って……後悔しても、知らないよ?」
「言ったろ、好きにさせてやるって。」
ふたりはベッドにもつれ込んだ。深いキスをしながら、カカシは性急に服を脱がせにかかる。ボタンをはずしてシャツをはだけ、ベルトの金具も取り去ってズボンとパンツを降ろした。
サスケは膝まで降ろされたズボンとパンツを足だけで脱ぎ去ると、カカシのワイシャツのボタンに手をかける。
唇を離す。上気した頬、熱い吐息、そして蕩けたまなざし。……今、すぐにでも一緒になりたい。
カカシは自分で服を脱ぎ去って、サスケのシャツも脱がせ、生まれたままの姿になった。ふたりともそこはもう立ち上がっていて芯を持っている。お互いにそれに手を伸ばした。芯を持っていたそれがどんどん硬くなっていく。
「っはぁ、っは、」
また唇を合わせる。お互いに舌を絡めて、口腔内をなぞって、交じり合った唾液を飲み込む。その間も、お互いを扱く手は止めない。
「っあ、はぁっ、んっ……」
先に射精感が来たのはサスケだった。
「ッカシ、も、出る、出るっ……!」
カカシの手つきが早くなる。サスケはピクンと身体を揺らし、カカシの手の中に精を放った。
「っあ、……っ」
はぁっ、はぁっ、はぁっ
ふたりの荒い息が交差する。
カカシはサスケの後ろの穴に精液を擦り付けると、ゆっくりと中指を沈めていった。内壁をぐるりとなぞって、前立腺の裏を探り当てると、そこを擦りながらゆっくりと抽送を始める。
「ッぁ、んんっ、あっ、……っ!」
ピクンと反応しながら、その指がもたらす快感を拾い、声が漏れ出た。
「サスケ、ここ、気持ちいい? 痛くない?」
「だい、じょうぶっ、んっ、気持ちいっ……。」
指が二本に増えてその動きが早くなる。出入りするたびにそこはクチュ、クチュ、と音を立てる。その淫猥な音が耳に届いて、どんどん興奮していく。
「あぅっ、……あ、はぁっ、あっ、ぁあっ!」
蕩けていくサスケの顔を見て、また思わずその唇にしゃぶりついた。サスケはカカシの首に手を回す。
「んっ、んんっ、はっ……ん、んぅっ! んっ!」
指が四本に増えて、中を押し広げるようにうごめいた後、ぬる、と指を引き抜いた替わりにカカシのそれがあてがわれた。
「はぁっ、サスケッ、良い? 挿れたい……っ」
サスケはカカシの首にしがみついたまま頷いた。
カカシのそれがゆっくりと穴を押し拡げ入ってくる。その圧迫感、異物感にサスケの眉間に力が入る。少し入れては抜いて、もう少し入れては抜いてを繰り返しながらゆっくりと奥へ奥へと沈めていき、それがサスケの前立腺の裏に届くとサスケの身体がピクンと跳ねた。
「……あ、んあっ!」
異物感が徐々に薄れていく。はぁっ、はぁっとふたりで荒い息を吐き、浅い抽送を繰り返している内に圧迫感はなくなっていって、残ったのは背筋を駆け抜けるような快感だった。
「あっ、あ! はぁっ、っあ、ぁあっ! あっ、ぅあっ!」
カカシは動きを止めて、サスケの後頭部に手を添える。
「サスケ、苦しくない? ……奥まで、挿れていい?」
「っいい、もっと奥っ、まで、っ……!」
サスケの頭を撫でた後、ぐぐぐっと腰を奥に進めると、また抽送を始める。徐々に動きを早くしていき、ボルテージを上げていった。
「あっ! あ、あぁっ、あっ、ぅ、ぁっあ!」
サスケがぎゅっと首にしがみつき、カカシの耳のすぐ横で喘ぐ。嫌でも興奮する。そうでなくても興奮しているのに。
ああ、このままずっとこうしていたい。サスケと奥までつながったまま、サスケの声を聞きながら、サスケを抱きしめながら。
「っあ! ……っあ、カカ、あっ! カカシっ、はぁっ、気持ちい、いいっ、もっと、もっ、……っ!」
サスケに急かされて、腰の動きをぐんと早くする。
「はぁっ、サスケっ、サスケっ……!」
パンッパンッパンッパンッ
「あぁっ! あ、あっ! っあ、は、あっ! ッカシ、あぁっ!」
「……っも、出るっ……!!」
ググッとひときわ奥に打ち付けた。ドクッドクッとカカシのそれが脈動する。
「……っあ、はぁっ、はぁっ、……あっ……」
中でその鼓動を感じながら、サスケはしっとり汗ばむ背中に手を回し、ぎゅっと力を込めた。
「サスケ、このまま、……このままでいたい。繋がったままでいたい。いい……?」
「俺も……、しばらくこのままで……。」
カカシがサスケの身体を支えて横向きになる。
熱いものが奥に入ったまま、繋がったまま、どちらからともなくキスをする。
こうして繋がっていられるのもあと少し。その後はただの先生と生徒に戻る。そしてサスケは卒業していって、金曜に抱きしめ合いながら眠ることもなくなる。
今のこの時間が永遠に続けばいいのに。射精したそれは硬さを失い小さくなっていく。それに寂しさを覚えたのはサスケも同じだった。
「なぁ、サスケ……お前にとっての特別って、何……? 好きになったわけじゃ、ないんだよね。じゃあ、特別って……?」
カカシがサスケの前髪をサラッと撫でる。
「……わかんねぇよ。俺にも。ただあんたになら、身体を預けてもいいと思った。二年半も、ずっと俺のことを考えてくれたから。大事にしてくれたから。
……今までの二年半、俺を想ってくれてた事は忘れないし、感謝もしてる。今日のことだって、俺は忘れない。」
サスケのまっすぐな眼差しにこころが射抜かれる。もう、終わるのに。もう、こうして会う事はなくなるのに。好きだという気持ちはどんどん膨れ上がっていく。
「俺も、忘れらんないよ。今日で終わりになんかしてほしくない。隣り合って眠るだけの関係でいい。……でもサスケにはもう、金蔓は必要ない、んだよな。」
「ああ、金蔓のあんたは、もう俺には必要ない。」
サスケの言葉に、胸がズキンと痛んだ。
特別だなんて言ったって、俺はサスケにとってはやっぱりただの金蔓なんだ。そしてもう金蔓が必要ないサスケにとって、俺はもう必要ない。ずっと覚悟し続けてきたことだ。この関係はいつか終わると。そしてサスケは俺の手の届かない遠くに行ってしまうと。でもいざその時になると、女々しい感情が溢れ出てくる。バカだな、俺は。
「金蔓は必要ない、けど……あんたはもう、金蔓じゃない。俺にとって特別な人間だ。それは、この二年半の記憶が薄れない限り、この先もずっと変わらない。」
期待してしまう自分が嫌だ。もしかしたら進学してからも会ってくれるんじゃないかと思ってしまう。そんな都合のいい話なんて、あるわけがないのに。
「特別、って、どういう意味なの? サスケの特別になれたら、今までと何が変わるの?」
「俺にもわかんねえよ。……ただ、一緒に居たいと思う。一緒に眠っているときは胸が満たされる思いがする。身体を預けてもいいと思った。身体を預けてみて……。今まで幸せなんて感じたことがなかったけど、ああきっと今の俺のこの満たされた感覚は、幸せってやつなんだろうなと思った。」
カカシの胸の鼓動が早くなる。それって、それって……
「……好き、とは違うの?」
「好き……、好き、なのかもしれない。人を好きになったことなんかねえから、わかんねぇ。」
「好き、なんだとしたら、一緒に居たいと思うのなら、これからも……」
サスケの手がカカシの口を塞ぐ。
「こうして会うのは、今日で最後だって言っただろ。」
……ああ、期待なんてするんじゃなかった。これからもこうして会えるかもしれないなんて、バカなこと考えるんじゃなかった。いくら特別だって言ったって、サスケにとって俺はやっぱり、もう必要のない人間なんだ。
これが最後なら、せめて笑顔で別れよう。いつものようにサスケのアパートまで送って、笑顔で手を振って、それで俺とサスケの関係は終わりだ。終わるんだ。
「……ごめんね、困らせるようなこと言って。わかってる。今日で終わりだって。」
繋がっていたそこからカカシのものを抜く。もう一度だけサスケを抱きしめて、笑顔を作って、起き上がると浴室に向かった。
「おい、カカシ……」
サスケも起き上がるが、浴室に入っていくカカシを見送っただけだった。
忘れられない、こんな最後、忘れられるわけがない。求め合うようなキスをして、深く繋がって、そうして幸せを感じられただけで充分だ。
明日からはもうただの先生と生徒に戻る。今日の思い出を大切に胸にしまって俺は日々過ごしていくんだろう。また会えたら、なんてくだらないことを考えながら、年度終わりの雑務に追われて、新入生を迎える準備をして。慌ただしく過ぎていく日々に、サスケがいない事実を突きつけられながら、もう会う事はないんだと思い知らされながら時間だけが過ぎていくんだろう。
さっとシャワーを浴びて脱衣所に出ると、そこにはサスケが待っていた。俺はニコッと笑って「俺はもうシャワー終わったよ」とバスタオルを手に取る。ああ、今の俺はうまく笑えてただろうか。あとぐされのない最後にするために笑顔でいなきゃいけないのに、表情筋がいつもよりもうまく動かせない。
サスケは黙って浴室に入っていく。身体の水滴をバスタオルで吸って、俺は脱ぎ散らかした服を身につけていく。
そうしている内にサスケも浴室から出てきて、バスタオルを手に取り、身体を拭いていく。
笑顔で、手を振って、別れる。
そんな簡単なことが、今はとてつもなく難しいことに思える。
身体を拭き終わったサスケが服を着込むと、部屋に備え付けてある電話から受付に「もう出ます」と連絡した。
「……カカシ、俺は」
「言わないでい良いよ、わかってるから。」
手を差し出すと、いつものように恋人繋ぎをして部屋から出る。受付でお金を払って、噴水のある駅前に来ると、胸がギュッと痛んだ。
それを悟られないように、いつものように通り過ぎて、サスケのアパートに着いて、俺は笑顔を作る。
「ちゃんと鍵かけるんだよ。」
あとは手を振って階段を登る後ろ姿を見送った後、自分の家に帰るだけだ。
「カカシ、俺はあんたとこうして会うのは最後だけど……」
「うん、わかってるよ。」
「わかってねえだろ。」
「わかってるから、それ以上言わないで。お願いだから。もう時間も遅いし、早く帰りな?」
笑顔を顔に貼り付けたまま、手を振る。
サスケは小さく「ウスラトンカチが……」と呟いて、階段を上がっていった。
俺はいつものように帰路につく。
卒業式が終わって、終業式が終わって、年度が変わり、俺はまた一年の学年主任と生徒指導を任された。
新一年生達は少し緊張しながら授業に耳を傾ける。
無意識のうちに、熱心にノートを取るサスケの姿を探してしまう。その度に俺は、バカだなと自嘲する。
新一年生の個人懇談会も終えて少し落ち着いてきた頃に、職員室で生徒に配るプリントをまとめていると、机の上に置いたスマホがピロンと通知を知らせた。何気なしにロック画面に目を向けると、サスケからのLINEだった。目を擦ってもう一度見る。やっぱりサスケからだ。
ロックを解除してトーク画面を開く。
『今日、時間あるか。』
俺はもう一度目を擦る。
書いてある文字列は変わらない。
『二十時くらいなら。俺とはもう会わないんじゃなかったの?』
送信ボタンをタップして、返事が届くのを待つ。トン、トン、トン、と指でデスクを叩きながら。
ピロン、と通知が鳴った。
『金曜の夜に会うのは最後だと言ったんだ。なのにあんたが話を遮って聞こうとしないから。本当にウスラトンカチだな。』
思わず、口元が綻んだ。
また、会える。
サスケに、会える。
「ハハ……バカだな、俺。ほんとバカだ。」
傷つきたくなくてサスケの言葉を聞かないようにして勘違いして一人で凹んで。
カカシはトーク画面にメッセージを入力して、送信ボタンをタップする。
金曜の約束はもう終わった。
けど、これからは都合がつけばいつでも会える。それが嬉しくて嬉しくて、たまらなかった。
『じゃあ、二十時にスタバの前で。』
カカシはスマホをデスクに置いて、時計を確認してから、仕事に取り掛かった。